
こんな疑問に答えます。
こんにちは、ショーイです。
読書が好きで、年300冊ほど読んでます。
この記事では、読書のメモに最適なアプリだけでなく、アプリ以外のおすすめのメモのとり方から、メモを活かして学びに繋げる方法まで解説します。
本記事の内容
- 読書メモアプリ5選【デメリットも】
- アプリ以外におすすめの読書メモのとり方
- 読書メモの活かし方
読書メモを取ることは大事ですが、メモを取るだけでは不十分。
読書メモをもとに、人生を豊かにしていきましょう!
記事の最後では、読書知識を定着させる「最強の方法」まで紹介するので、お見逃しなく。
※0円の「プロによる要約本」という近道
最近は無料の高品質の要約も増えており、最初の基礎ベースを身につけるならプロによる本要約サイトの「flier(フライヤー)」を参考にするのがおすすめ。flierは1週間の読み放題無料体験もあるので、これを使ってまずは0円でプロの要約を読むのもありですね。
» 本要約サイト「flier」の無料お試しはこちら
» flierの評判&口コミ記事はこちら
読書メモアプリ5選【デメリットもある】
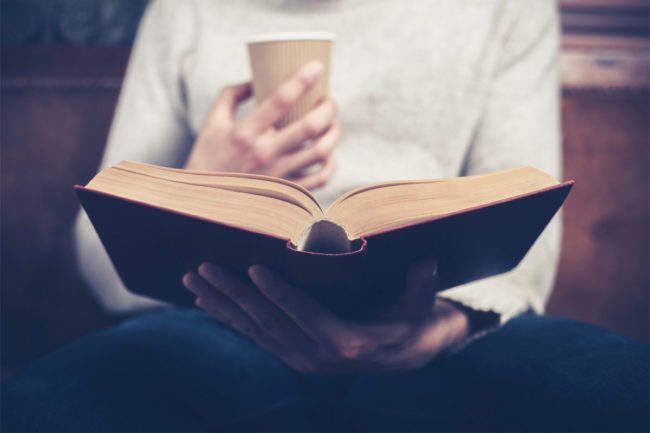
ではさっそく、読書のメモに最適なアプリ5選を簡潔に紹介します。
1:ブクログ
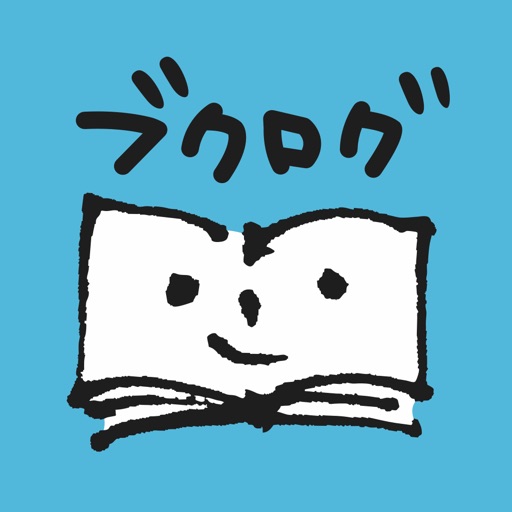
イチオシの読書メモアプリは「ブクログ」です。
特徴やデメリットは下記の通り。
ブクログの特徴
- 「知らない本と出会える」がメインコンセプト
- 新刊情報、ランキングが充実している
- 書店をイメージしたデザインがきれいで可愛い
- 他のユーザーと交流ができる
- バーコード読み取り機能や検索機能などもある
ブクログのデメリット
- シンプルな読書メモアプリとしては使いにくい
- 使っていること自体に満足してしまう
きれいなデザインですが「読書メモアプリとしては、多機能すぎるかな」という感じです。
2:読書メーター

続いておすすめの読書メモアプリが「読書メーター」です。
特徴やデメリットは下記の通り。
読書メーターの特徴
- 本の冊数、読書量、著者別など様々なグラフが視覚的に把握できる
- SNSのようなコミュニケーションも可能。
- その他にもコミュニティや友人登録なども
- バーコードの読み取りや、新刊情報通知も
読書メーターのデメリット
- こちらも純粋な読書メモアプリとしては使いにくい
- 使っている人の読書感想レベルはあまり高くない
ブクログと同様に、多機能で他の読書好きと交流も可能ですが、読書メモアプリとしてはシンプルさに欠けるところはありますね。
3:ビブリア

つづいては「ビブリア」。
特徴やデメリットは下記の通り。
ビブリアの特徴
- 交流や他の人のレビューなどがなくシンプルな作り
- バーコード読み取り機能あり
- 読んだ本の一覧を表示できる
- 読書量はグラフでも見られる
- ブクログや読書メーターにリンクがあるのでレビューなども一応見れる
ビブリアのデメリット
- シンプルすぎて飽きる
- アプリで管理しなくてもいいように感じる
単純な読書メモアプリとして使うにはいいかもですが、「これだったら、わざわざアプリを使わなくてもいいのでは?」と僕なんかは思ってしまいます。
4:Readee

楽天がリリースしている読書管理アプリです。
それ以外の機能は似たりよったりなので、楽天を使わない人は特に選ぶメリットはないかなと。
5:蔵書マネジャー
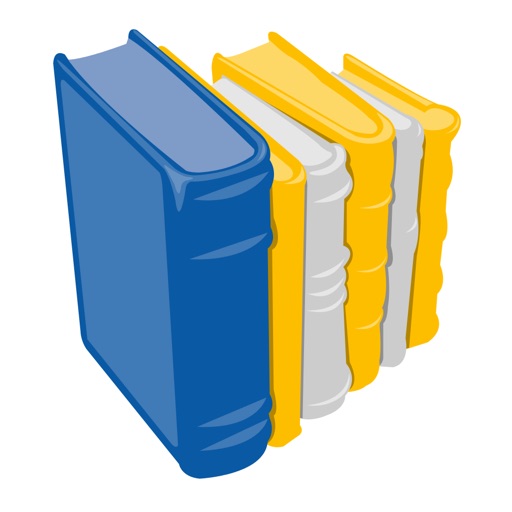
とにかくシンプルなのは「蔵書マネージャー」。
「だったらビブリアの方がいいかな?」とも思いますが。
読書メモをアプリで取ることのデメリット
以上、読書のメモにおすすめのメモアプリ5選を紹介してきました。
ここまで紹介してきてなんですが、読書のメモにアプリを使うことはあまりおすすめしません。
理由は下記の通り。
- 読書中にスマホ片手にメモするのは、集中力を落とす原因になる
- メモを取ること以外の機能がありすぎて、読書に集中できない
読書アプリは読み終わった本の管理には向いていますが、読書中にアプリでメモを取るのは集中力を途切れさせる原因です。
なので僕のおすすめは、紙のノートにメモする王道のやり方か、Kindle専用端末によるメモです。
以下で僕が実際にやっているメモのとり方を解説します。
プロによる要約が、今なら【無料で読み放題】
今話題の本をプロによる高品質な要約で読めるサイト「flier(フライヤー)」が今なら【無料で読み放題】。
さらに期間限定で10%オフのキャンペーン中なのでお見逃しなく。
» 本要約サイト「flier」の無料お試しはこちら
» flierの評判&口コミ記事はこちら
アプリ以外におすすめの読書メモのとり方

紙の本でメモを取る場合と、Kindleなどの電子書籍でメモをとる場合を解説します。
※Kindleなどの電子書籍が圧倒的に楽です。
紙の本でメモを取る場合
紙の本でメモを取る場合は、基本的には付箋を使って、気になるところに印をつけます。
読書でメモすべきなのは、自分がどんなことを思ったのか、どんな考えを持ったのかについてです。
それ以外は付箋でも、ハイライトでもいいので、印をつけておくだけいいですよね。
» 【読書メモの取り方】科学的に正しい3つのメモ術&おすすめ媒体
マークした文章から重要な文章は書き出す
読み終わった後に、付箋やハイライトでマークした文章を見直します。
- 知識として記憶したい文章
- 印象に残った文章
- より深堀りしたい文章
こういった文章を中心に書き出し、更に詳しく自分の考えや思ったことをノートに書いていきます。
さらにくわしい付箋でのメモのとり方は、下記記事で解説しています。
» 【用途別】読書の『付箋』3つの使い方【年300冊読む読書家が解説】
直接書き込みが最強
紙の本に書き込んで本を汚したくない方も多いと思いますが、直接書き込むのは、効率的には最強の読書メモになります。
- 気になる文章は線を引くか、段落ごと囲って目印にする
- 簡単なコメントだけ余白に書き込んでおく
あとはコレを見返して、特に重要なところを読書ノートなりにまとめていけばいいわけです。
とはいっても書き込むのが嫌だという人も多いと思うので、上記で紹介したような方法でメモをとるか、Kindle専用端末で読書するのがおすすめです。
KindlePaperWhiteでメモをとる
僕は長い間紙の本だけで読書していましたが、ここ最近は、Kindleにある本はKindle専用端末のKindlePaperWhiteで読むようにしています。
理由は下記の通り。
- 文章のハイライトやメモ機能が備わっている
- 読書以外の機能がないので集中力も途切れない
- 持ち運びにも便利ですぐに本も購入できる
- 紙の本と同じような質感で読めるE-Inkで目に優しい
- ブルーライトもほぼないので寝る前にも最適
- 防水機能までついているので、お風呂でも読める
こんな感じで、けっこう最強です。
ハイライト機能
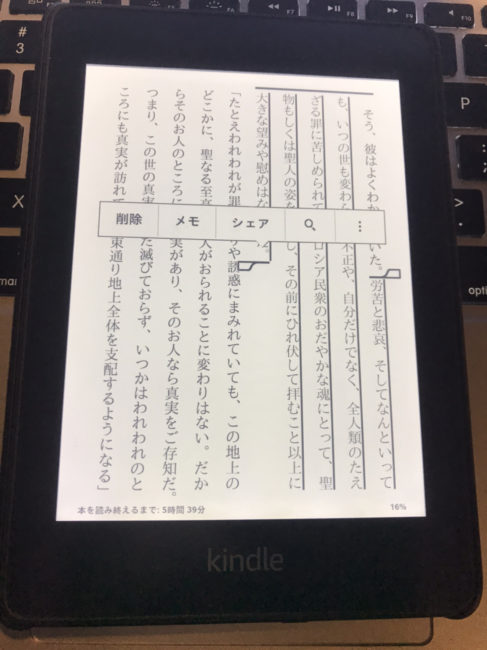
メモ機能
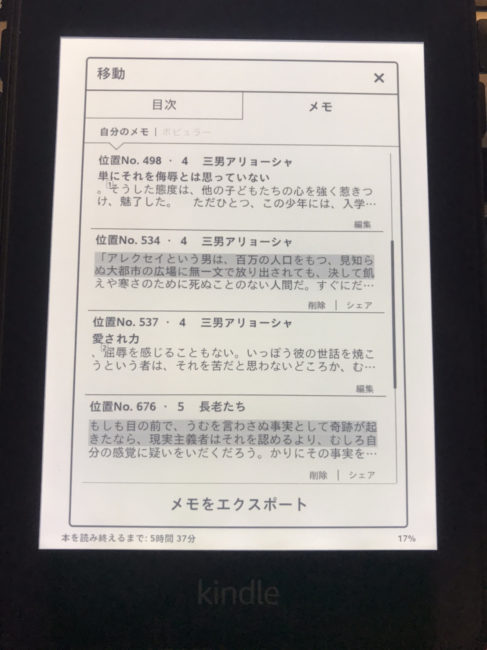
とはいっても紙の本にしかない魅力もやはり多く、今まで電子書籍を使っていない人は抵抗感も大きいと思います。
ですが慣れると読書メモがとても楽になるので、基本Kindleにある本は電子書籍で読むようにしています。
読書メモアプリでできることは、ほとんどできると思うので、ぜひ使ってみてください。
KindlePaperWhiteのレビュー記事はこちら👇
-
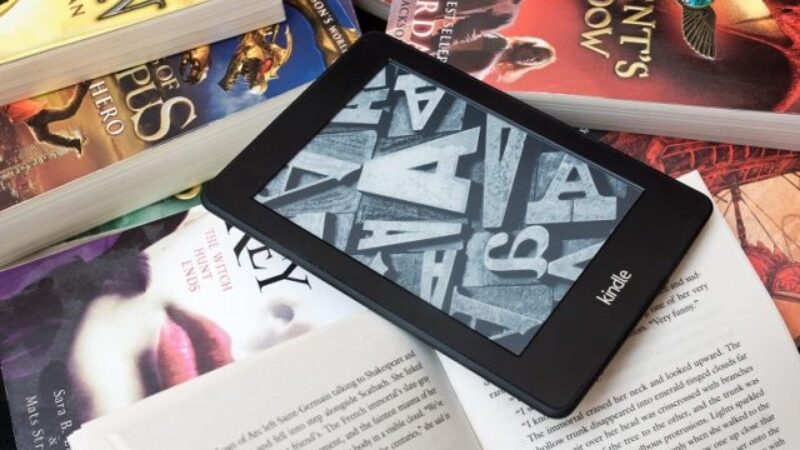
-
【買うな】KindlePaperWhite本音レビュー【紙の本1,000冊から乗り換え】
続きを見る
マインドマップを使った読書メモもおすすめ
マインドマップとは、頭の中で考えていることを脳内に近い形に書き出すことで、記憶の整理や発想をしやすくするノート術のことです。
具体的なイメージとしてはこんな感じです。
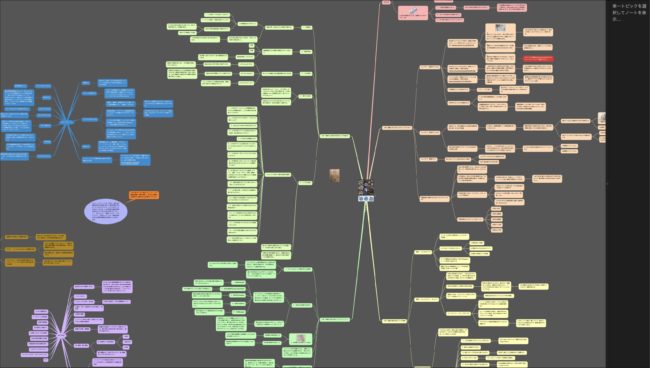
マインドマップ読書メモのメリットは下記の通り。
- 本全体を俯瞰して見られるので記憶に定着しやすい
- アプリを使えば画像挿入やリンク挿入もできて便利
- スマホでいつでも見直せるので、復習が簡単にできる
ざっと上げるだけでもメリットばかりです。
おすすめのマインドマップアプリ
まずは無料アプリでマインドマップに慣れたら、高機能なマインドマップアプリを買うといいかもです。
読書メモの活かし方

メモとは、要点を忘れないように記録しておくことです。
メモを活かして学びを得るところまでが大切です。
メモしたものは必ずアウトプットしよう
メモは飽くまでメモであり、メモしただけでは大した学習効果はありません。
アウトプットとは例えば下記のようなもの。
- 家族や友人に本の要点や自分の感想を話す
- SNSやブログなどで自分の考えを発信する
- 仕事や人生の行動や考え方に応用する
こういったアウトプット(発信、行動)が伴って初めて、読書からメモしたことが、意味のあるものになります。
おすすめなのは「読書ブログ」を作ること
アウトプットの中でもおすすめしたいのが、自分専用のブログを作成すること。
読書メモアプリで管理するのは楽でいいですが、アプリが突然使えなくなることも結構あります。
こんな感じで読書アプリは消えてしまうリスクが高かったり、アウトプット以外のメリットがありません。
僕も読書の要約記事をなどをブログで書いてます。参考までに。
-

-
【愛するということ】本の要約&感想|フロムの名言【愛は技術だ】
続きを見る
読書ブログのメリットは下記の通り。
- 自分が消さない限り、残り続ける
- 自分で広告も掲載できるので収益化も可能
- カスタマイズの自由度が高く愛着が湧きやすい
以下の記事で読書ブログの作り方を解説しているので、アウトプット先に困っている方は活用してみてくださいね。
-

-
【読書ブログの作り方】プロブロガー&読書家の僕が解説【感想・記録にも】
続きを見る
今回は以上です!
-

-
【悪い評判】本要約アプリ「flier(フライヤー)」本音感想【2年利用】
続きを見る
-

-
Audibleの感想【読書家がおすすめする、オーディブルの正しい使い方】
続きを見る
-

-
【読書メモの取り方】科学的に正しい3つのメモ術&おすすめ媒体
続きを見る
-

-
【用途別】読書の『付箋』3つの使い方【年300冊読む読書家が解説】
続きを見る
良い読書ライフをお送りください_(:3」∠)_





